このような悩みや困りごとはありませんか?
- 退職日をいつにすれば社会保険料が一番お得になるのか分からない
- 月末退職と1日前退職で、どれくらい手取り額が変わるのか知りたい
- 退職後の健康保険や年金の手続き、費用負担が心配
- 会社との退職交渉が不安で、スムーズに進められるか心配
退職は人生の大きな転機。せっかくなら、少しでも損をせず、気持ちよく新しい一歩を踏み出したいですよね。
しかし、退職日によって社会保険料の負担が大きく変わることは、意外と知られていません。
この記事では、社会保険料の仕組みや退職日選びのポイント、ケース別のシミュレーション、注意点、よくある失敗例まで、分かりやすく解説します。
退職日によって社会保険料が変わる仕組み
まず、なぜ退職日によって社会保険料の負担が変わるのか、その仕組みを押さえておきましょう。
社会保険料の基本ルール

社会保険料(健康保険・厚生年金)の基本ルールは、以下の3点が重要です。
- 社会保険料は「資格喪失日の前月分まで」支払いが必要
- 資格喪失日は「退職日の翌日」
- 社会保険料は日割り計算ではなく、1ヶ月単位で発生
このため、退職日が月末か月末の1日前かで、資格喪失日が変わり、支払う社会保険料の月数が変わります。
ちょっと分かりにくいので、具体例で説明しますね。
具体例
| パターン | 給与の締め日 | 給与の支払日 | 退職日 | 控除される社会保険料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 月末 | 翌月25日 | 在職中 | 前月分(1ヶ月分) | 毎月1ヶ月分ずつ控除 |
| 月末退職 | 月末 | 翌月25日 | 5月31日 | 前月分+当月分(2ヶ月分) | 最後の給与で2ヶ月分まとめて控除 |
| 月途中退職 | 月末 | 翌月25日 | 5月30日 | 前月分(1ヶ月分) | 当月分の社会保険料は不要 |
このように、わずか1日の違いで社会保険料の負担額が変わるため、退職日を決める際はしっかり確認しましょう。
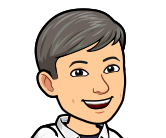
退職日によって厚生年金保険料の支払い月数も変わり、その分だけ将来の年金受給額に影響します。厚生年金は加入期間が長いほど、将来の年金額が増える仕組みです。
一方、退職日を「月末の1日前」にすることで社会保険料の負担が1ヶ月分減る場合がありますが、必ずしもそれが一番お得とは限りません。
退職後の健康保険料(国民健康保険・任意継続)の発生
会社の健康保険を喪失した翌月からは、国民健康保険または任意継続被保険者(会社の健康保険を継続する制度)に加入し、保険料を全額自己負担で支払う必要があります。
国民健康保険料や任意継続の保険料は、会社の社会保険料(労使折半)より高くなる場合が多いので注意が必要です。
月末退職と1日前退職の違いを図解
退職日を1日違えるだけで、社会保険料の負担が1ヶ月分変わることも。
ただし、その分、国民健康保険料や任意継続保険料の支払いが早く始まるという点にも注意しましょう。
退職日を月末にすると厚生年金の加入期間が1ヶ月長くなるため、将来の年金受給額がわずかに増える可能性がありますが、その分保険料も1ヶ月分多く支払うことになります。
退職後、国民年金に切り替わる場合は、月額1万7510円(2025年度)の全額自己負担となり、退職日によって切り替え時期も変わります。
| 退職日 | 資格喪失日 | 社会保険料の支払い | 退職後の健康保険料 | 手取りへの影響 |
|---|---|---|---|---|
| 月末(例:7月31日) | 翌月1日(8月1日) | 退職月分まで支払い(7月分) | 翌月(8月)から発生 | 社会保険料が2ヶ月分控除される場合あり |
| 月末の1日前(例:7月30日) | 月末(7月31日) | 前月分まで支払い(6月分) | 退職月(7月)から発生 | 社会保険料が1ヶ月分で済むが、国保等の支払いが早まる |
月末退職と月末1日前退職、どちらが得?ケース別まとめ
退職日を「月末」にするか「月末の1日前」にするかで、社会保険料や退職後の手取り額が大きく変わります。
どちらが得かは、家族構成や再就職の有無などによって異なります。
以下の表で、主要なケースごとの「得・損」や注意点を分かりやすくまとめました。
| ケース | 月末退職が得な場合 | 月末1日前退職が得な場合 | 注意点・補足 |
|---|---|---|---|
| 独身・再就職未定 | 会社の健康保険に長く加入できる 医療費自己負担が抑えられる | 社会保険料1ヶ月分を節約できる | 国民健康保険料がすぐ発生、保険料の試算が必須 |
| 扶養家族あり | 家族の保険保障を長く維持できる | 社会保険料1ヶ月分を節約できる | 家族の保険切替タイミングに注意 |
| 退職後すぐ配偶者等の扶養に入る | – | 社会保険料1ヶ月分を節約 国保負担なし | 扶養手続きが確実にできるか事前確認 |
| 再就職予定(入社日が月初) | – | 社会保険料の無駄払いなし | 新旧保険の空白期間がないよう入社日・退職日を調整 |
| 再就職予定(入社日が月途中) | – | 入社日直前退職で社会保険料の無駄払い防止 | 健康保険の空白期間が生じないよう注意 |
| 退職月に賞与(ボーナス)支給あり | 賞与支給日が資格喪失日以降なら保険料不要 | 賞与支給日が資格喪失日以降なら保険料不要 | 退職日と賞与支給日の関係を事前に確認 |
| 退職月にボーナス・退職金の支給あり | 支給日が退職日以降だと受給できない可能性 | 支給日が退職日以降だと受給できない可能性 | 会社の規程・支給日を必ず確認 |
退職日を調整する際の注意点
退職日を調整する際には、社会保険料の損得だけでなく、さまざまな制度や実務上の落とし穴に注意が必要です。
以下、より実践的かつ役立つポイントをまとめます。
会社との調整・事前確認
就業規則の確認は必須
退職日を自由に決められるとは限らず、会社の就業規則で「退職は月末のみ」「○カ月前までに申請」などの制約がある場合があります。希望する退職日が認められるか、必ず事前に確認しましょう。
賞与・退職金の支給条件に注意
ボーナスや退職金は「支給日在籍要件」など、支給日に在籍していることが条件の場合があります。
規定を満たさないと受け取れないため、支給日と退職日の関係を必ず確認しましょう。
有給休暇の消化も計画的に
有給を使って退職日を調整する場合、会社との調整や申請方法を早めに確認し、希望通りに取得できるよう準備が必要です。
会社都合・自己都合の違い
退職理由によって失業保険の給付条件が大きく変わります。
会社都合退職は給付開始が早く、日数も多い一方、自己都合退職は待期・給付制限期間が設けられます。
社会保険・健康保険の空白リスク
退職日と入社日の間隔に注意
退職日と次の入社日が離れると、健康保険や年金の「空白期間」が発生します。
この間は医療費が全額自己負担となり、万一の病気やケガで高額な出費になるリスクがあります。
空白期間の対処法
空白期間ができる場合は、以下のいずれかの手続きを速やかに行いましょう。
保険料の遡及請求・医療費の自己負担
未加入期間があると、後から保険料を最大2年分さかのぼって請求される場合があります。
また、未加入期間中の医療費は原則全額自己負担となります。
雇用保険・失業保険の受給と手続き
退職理由と受給開始時期
自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加え、2025年4月以降は1カ月(それ以前は2カ月)の給付制限期間があります。会社都合退職なら待期期間(7日)のみで受給が始まります。
離職票など書類の手配
退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」など必要書類を受け取り、速やかにハローワークで手続きを行いましょう。手続きが遅れると受給開始も遅れます。
受給資格の空白期間に注意
失業保険は退職から次の就職までの空白期間が1年未満でないと合算できません。1年以上空くと、直前の会社の加入期間しか反映されません。
その他の実務的な注意点
年末調整や確定申告
年末に退職する場合、会社で年末調整が行われないことがあります。その場合は自分で確定申告が必要です。
転職先との入社日調整
入社日が決まっている場合は、退職日と入社日の間に空白期間ができないように調整しましょう。どうしても間が空く場合は、上記の健康保険・年金手続きを忘れずに。
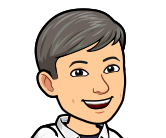
退職日は社会保険料だけでなく、賞与・退職金・健康保険・失業保険・家族の保障・税金など多面的に影響します。自分や家族の状況、転職先の条件、会社の規則を総合的に確認し、損得だけでなく「空白期間」や「受給資格」など実務上のリスクを最小限に抑えるよう調整しましょう。
任意継続保険料と国民健康保険料の違い・調べ方
任意継続保険料の調べ方
国民健康保険料の調べ方
給与が高い場合のポイント
任意継続保険料は標準報酬月額の上限(例:協会けんぽは32万円など)までしか計算されません。
そのため、国民健康保険料よりも任意継続保険料の方が安くなるケースがあります。
例:月収80万円(年収960万円)の場合、国民健康保険料は月額6.8万円程度になることもありますが、任意継続保険料は上限(例:32万円)に基づいて月額3万円台となるため、任意継続の方が安くなる。
健康保険組合によって上限額は異なるため、必ず最新の情報を確認してください。
協会けんぽのホームページ
全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式サイト
保険料率や最新情報、任意継続に関する詳細も掲載されています。
厚生年金保険料は、退職後は原則として支払い義務がなくなります。
ただし、退職時点で60歳未満の場合、国民年金に加入し、国民年金保険料を支払う必要があります。
国民年金保険料は2025年度で月額1万7510円、2026年度は1万7920円となり、全額自己負担です。
退職日によって、国民年金保険料の支払い開始時期が1ヶ月前後するため,家計への影響も考慮しましょう。
- Q退職月に賞与(ボーナス)を受け取った場合、社会保険料はどのように控除されますか?
- A
退職月に賞予(ボーナス)が支給される場合、その賞与に対しても社会保険料がかかるかどうかは、賞与の支給日と退職日(資格喪失日)の関係によって異なります。
→ その賞与は「在職中」に支給されたものとみなされ、社会保険料が控除されます。
→ その賞与は「退職後」に支給されたものとみなされ、社会保険料は控除されません。たとえば、7月31日退職(資格喪失日8月1日)で、賞与支給日が7月30日なら社会保険料がかかりますが、8月1日以降なら社会保険料はかかりません。
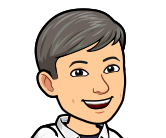 たむたむ
たむたむ注意点
- Q退職後に社会保険料の請求が来ることがあるのはなぜ?
- A
会社が社会保険料をまとめて控除している場合や、退職月分の保険料が未納のままになっている場合、後日請求が来ることがあります。会社とよく確認しましょう。
- Q入社月に退職した場合(同月得喪)はどうなる?
- A
入社した月に退職した場合、厚生年金は保険料が還付されることもありますが、健康保険は同月内で再加入しても還付されません。
同月得喪の場合は、会社や年金事務所に還付の有無を確認しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
退職は人生の大きな節目。少しの知識と準備で,大きな安心と節約につながります。
分からないことや不安なことがあれば,専門のサポートサービスも活用しながら,納得のいく退職を実現してくださいね。
※本記事は2025年5月時点の法令・制度に基づき執筆しています。最新情報は各自治体や社会保険事務所,専門家にご確認ください。
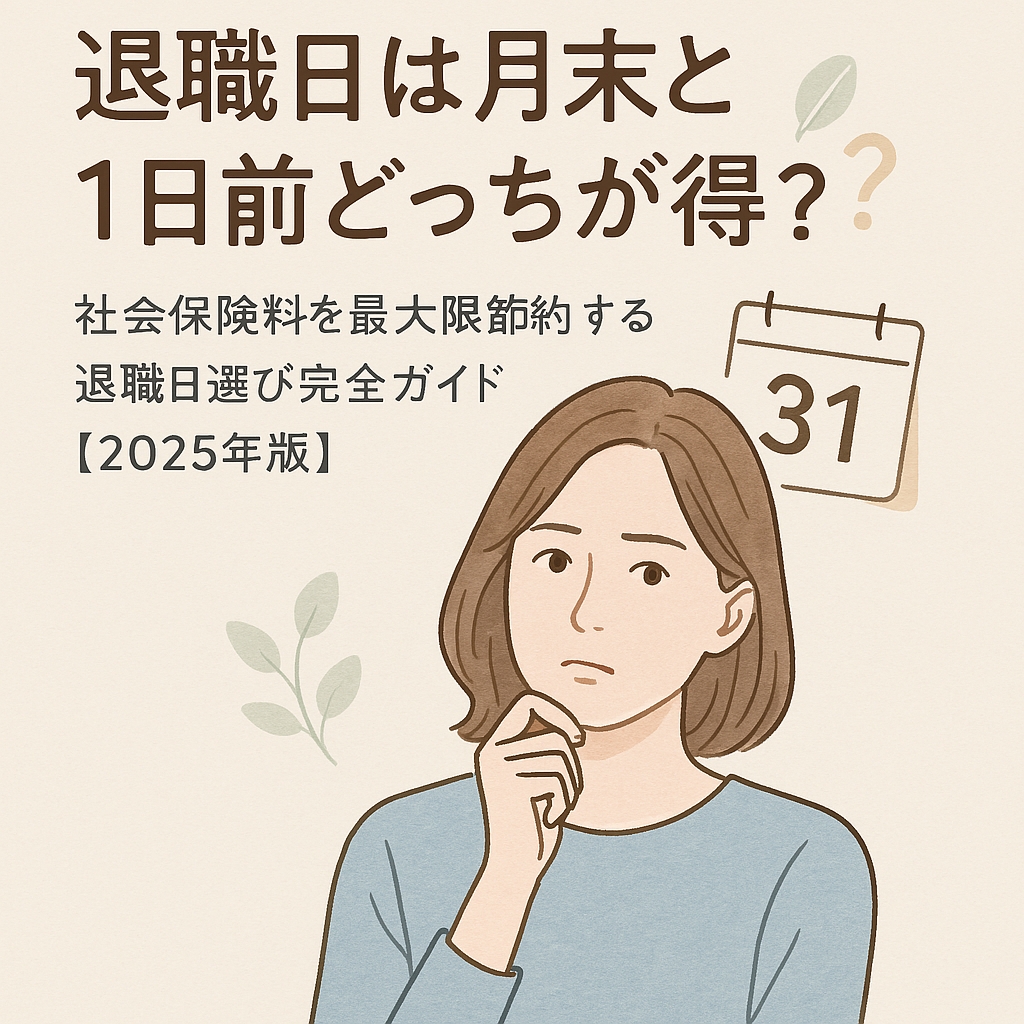


コメント