【はじめに】──あなたの「今」の苦しみは、決して無意味じゃない
そんな思いを抱えながら、毎日を必死に生きているあなたへ。
うつ病や適応障害で退職を考えることは、決して“逃げ”や“弱さ”ではありません。 むしろ、あなたの心が「これ以上は危険だ」と叫んでいる、本能的なSOSです。
多くの人が「自分が悪い」「もっと頑張らなきゃ」と自分を責めてしまいがちですが、 限界を感じている自分を責める必要はまったくありません。
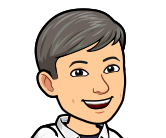
あなたは、もう十分に頑張りました。これからは自分の人生を守るための選択をしてもいいのです。
うつ病や適応障害で退職を考える方の多くが、「本当に辞めていいのか」「自分に甘いのでは」と自責の念に苦しみ、同時に「会社への伝え方」「生活費や手続きなど現実的な不安にも悩まされます。
私は再就職支援の現場で、前職で精神的なダメージを受け、その後も心の傷が癒えず、長く苦しみが尾を引いているクライアントを何人か見てきました。
たとえば、職場で同僚からイジメのターゲットにされ、精神的に参ってしまい退職に至った方が、その経験による心の傷がなかなか癒えず、退職後も再就職や社会復帰に大きなハードルを感じてしまうケースがあります。
「辞めたい」は“甘え”じゃない。あなたの心のサインを信じて
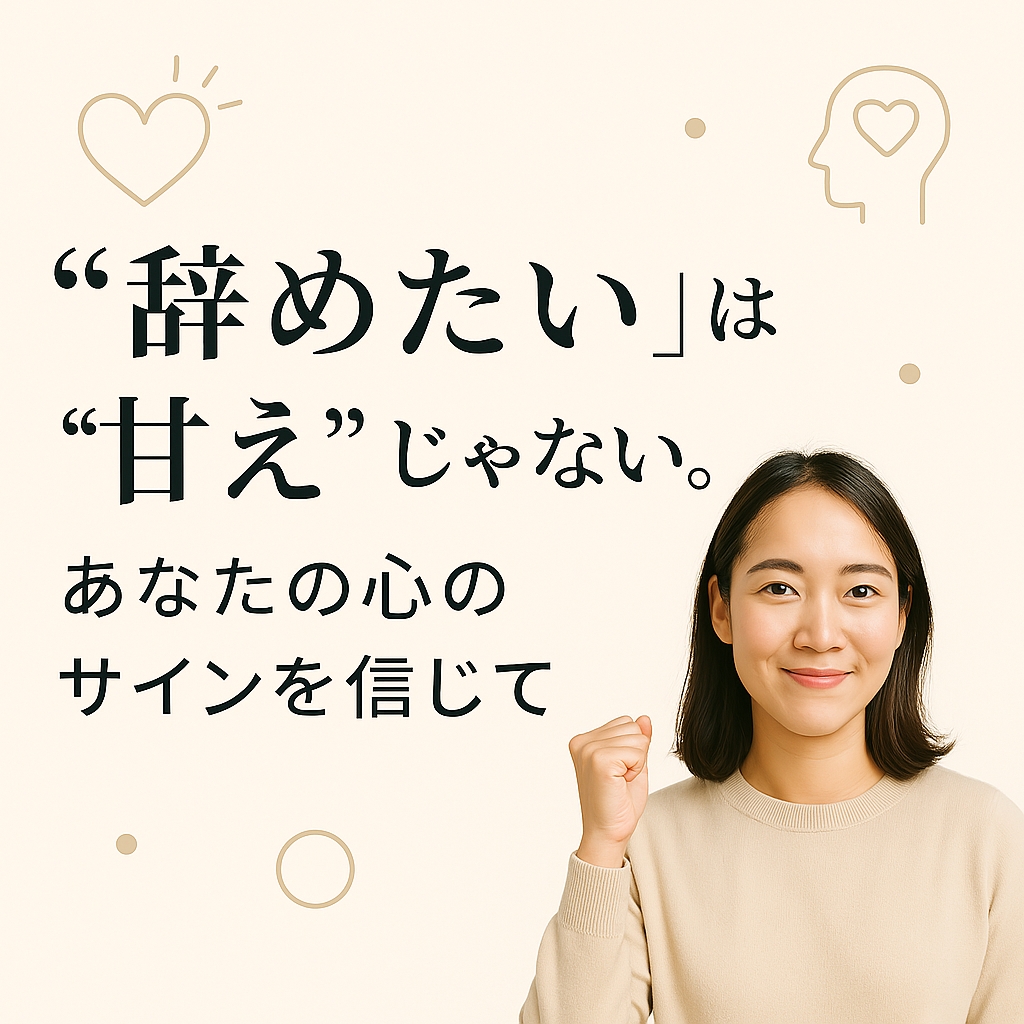
うつ病や適応障害で苦しんでいると、「本当に辞めていいのか」「自分に甘いのでは」「また同じことを繰り返すのでは」と、 不安や罪悪感に押しつぶされそうになることがあります。
しかし、退職を考えるほど追い詰められているということは、すでにあなたは限界まで頑張ってきた証拠です。
退職は“負け”じゃない
「辞める=負け」ではありません。 むしろ、自分を守るための“勇気ある決断”です。
人生は一度きり。あなたの心と身体は、何よりも大切な“資産”です。
「辞めたい」と感じているあなたは、もう十分頑張ってきました。自分を責めるのではなく、これからの人生をどう生きるかに目を向けてほしいと思います。今のあなたには、その一歩を踏み出す価値があります。
心の不調は体にもサインとして現れる
精神的な不調は、心だけでなく体にもさまざまなサインとして現れることがあります。
例えば、以下のような症状が出ることがあります。
こうした体のサインは、「もう無理しないで」という心からのメッセージです。
無理に我慢を続けてしまうと、心身ともにさらに追い詰められてしまうこともあります。
自分の心と体の声に耳を傾けて
「辞めたい」と感じるのは、あなたが弱いからではありません。心や体が限界を迎えているという、大切なサインです。自分を責めず、まずは自分の心と体の声にしっかり耳を傾けてあげてください。
あなたの健康と幸せが、何よりも大切です。無理をせず、自分を守る選択をしても良いのです。
| 悩みの内容 | 具体例 |
|---|---|
| 退職しても大丈夫か | 生活費・将来への不安 |
| 会社への伝え方 | どう切り出せばいいか、トラブルにならないか |
| 自責感・罪悪感 | 「自分に甘いのでは」「逃げではないか」 |
| 退職後の社会復帰 | 再就職できるか、心の傷が癒えるか |
退職を決断する前に、まず知っておきたい「安心の知識」
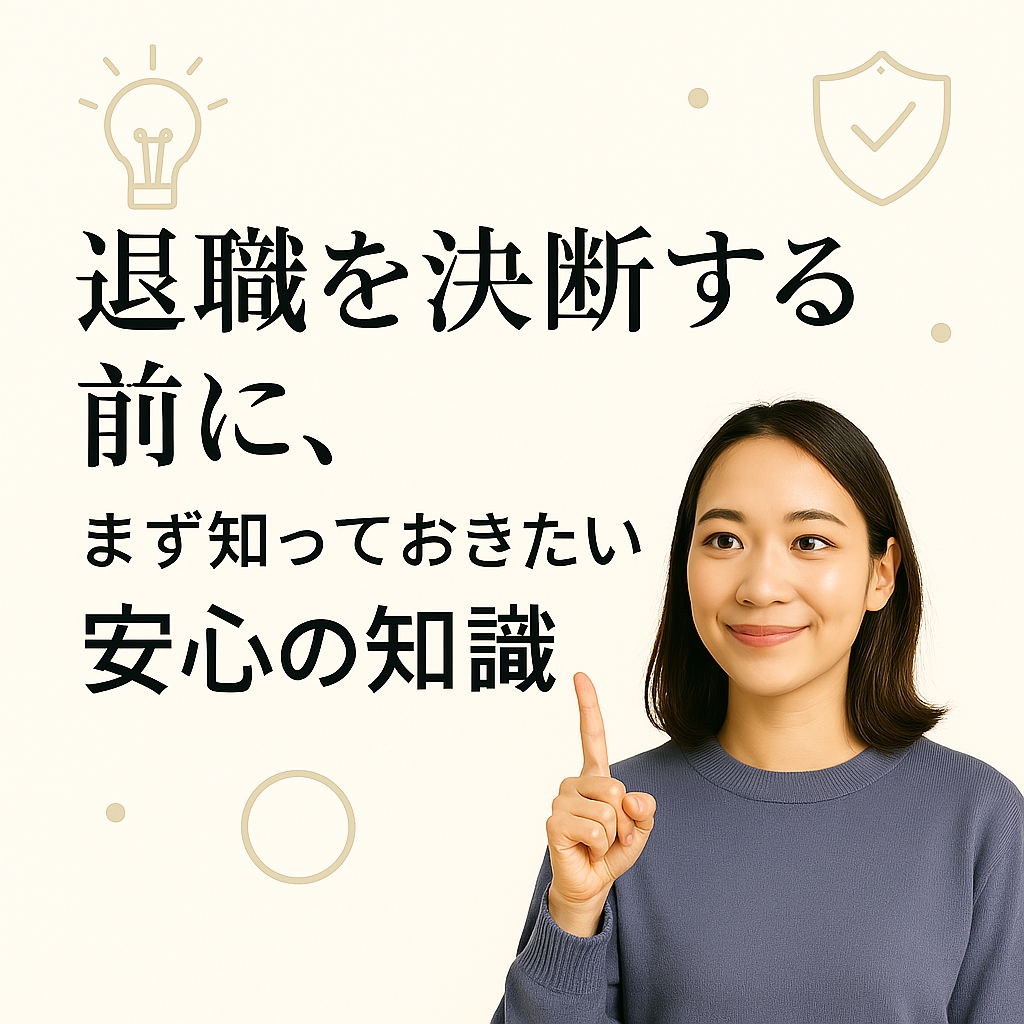
まずは専門家に相談しよう
休職制度の活用
会社によっては「休職制度」があります。一定期間、職場に籍を残したまま療養でき、社会保険も継続されます。
さらに、休職中は健康保険から「傷病手当金」という給付金を受け取れる場合があります。
これは、業務外の病気やケガで働けなくなった際に、給与の約3分の2が最長1年6ヶ月間支給される制度です。
生活費の不安を和らげながら、治療や回復に専念できます。
「辞める前にまず休職してみる」という選択肢も、あなたの負担を減らす大きな助けになります。
退職を決断する前に考えたいこと
休職制度が使えるかどうか、会社の就業規則を確認しましょう。
休職が難しい場合や、心身の限界を感じている場合は、退職の準備を始めましょう。
| 相談相手 | 相談内容の例 | メリット |
|---|---|---|
| 医師・カウンセラー | 症状・診断・休職/退職の判断 | 客観的な意見・診断書の取得 |
| 家族・友人 | 気持ち・生活の不安 | 精神的な支え・現実的なアドバイス |
| 労働組合・社労士 | 会社との交渉・制度の確認 | 法的なアドバイス・手続き支援 |
退職・転職のメリットとデメリット
退職や転職を検討する際には、心身の健康や今後の生活にどのような影響があるのか、多くの方が悩まれるポイントです。
ここでは、退職・転職によって得られるメリットと、注意すべきデメリットを整理しました。ご自身の状況と照らし合わせながら、今後の選択の参考にしてください。
| 相談相手 | 相談内容の例 | メリット |
|---|---|---|
| 医師・カウンセラー | 症状・診断・休職/退職の判断 | 客観的な意見・診断書の取得 |
| 家族・友人 | 気持ち・生活の不安 | 精神的な支え・現実的なアドバイス |
| 労働組合・社労士 | 会社との交渉・制度の確認 | 法的なアドバイス・手続き支援 |
会社への退職の伝え方・手続き・診断書の活用法
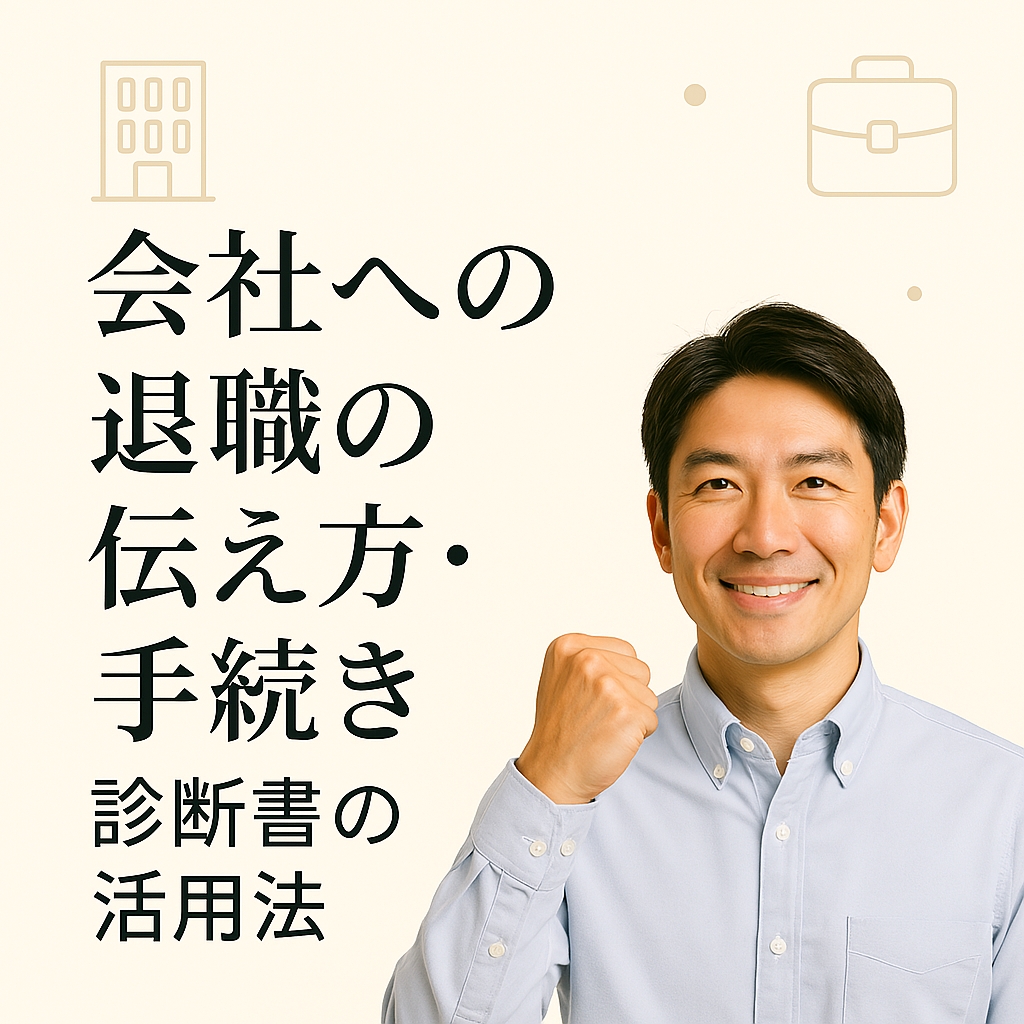
会社への退職の伝え方
退職を伝えるのは勇気がいりますが、あなたの健康が最優先です。
「体調不良が続いており、医師から休養が必要と診断されました。
大変心苦しいのですが、退職させていただきたくご相談させていただきました。」
| 方法 | ポイント | 例文 |
|---|---|---|
| 対面・電話 | できるだけ早く直属の上司に伝える | 「体調不良が続いており、退職を希望します」 |
| メール | 体調が悪い・直接話せない場合に有効 | 「体調不良が続き、退職を希望します」 |
退職理由の伝え方
「一身上の都合」「健康上の理由」などで十分です。 病名や詳細な事情を伝える必要はありません。
体調不良が続いており、医師から休養が必要と診断されました。
大変心苦しいのですが、退職させていただきたくご相談させていただきました。
急なお願いとなりご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
退職日や引継ぎ等につきましては、ご指示をいただけますと幸いです。
診断書の取得と活用
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | かかりつけの医師に「会社提出用の診断書が必要」と伝える |
| 2 | 病名や「休養が必要」といった内容を記載してもらう |
| 3 | 診断書はコピーを取り原本を会社へ提出 |
有給休暇の消化
退職前に有給休暇を消化するのはあなたの権利です。
会社の方針によっては消化できない場合もあるので、事前に確認しましょう。
退職後に「絶対使える」公的制度&手続き

公的支援制度まとめ
| 制度名 | 対象者 | 主な条件 | 支給内容 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 健康保険加入者 | 1年以上被保険者・休業中 | 給与の約2/3を最長1年6ヶ月 |
| 失業保険 | 雇用保険加入者 | 退職後、再就職の意思あり | 条件により数ヶ月間の給付 |
| 自立支援医療制度 | 精神科通院者 | 医師の診断書で申請 | 医療費自己負担1割 |
正しい知識が退職後の安心を支える
退職後の生活を安定させるためには、傷病手当金や失業保険などの公的制度を的確に活用することが不可欠です。
例えば、再就職支援の現場でクライアントと面談する中で、「退職後は傷病手当金を受給できない」と誤解されている方がいらっしゃいましたが、一定の条件を満たせば退職後も受給可能であることをご説明し、安心していただけたケースがありました。
また、「退職日に出勤してはいけない」という重要なルールをご存じなかったため、うっかり最終日に出社してしまい、結果的に傷病手当金を受給できなかったという事例も見受けられました。
こうした事例は結構あります。
特に傷病手当金については、要件を満たせば退職後も最長1年6ヶ月間受給することが可能ですから、しっかり要件を確認しておきたいところです。
また、失業保険(雇用保険)についても、病気やケガによりすぐに就労できない場合、「受給期間延長」の手続きを行うことで、最長4年間まで受給開始時期を繰り下げることができます。
労災という選択肢:精神疾患の場合の現実と課題
業務による病気やケガの場合は「労災保険(労働災害補償保険)」が適用されます。
精神疾患(うつ病など)の場合も、業務による強いストレス等が原因であれば労災認定の対象となりますが、認定のハードルは高く、認定率は30~35%程度と低調です。
ただし、近年は精神障害の労災請求・認定件数が増加傾向にあります。
主な退職後の公的支援制度まとめ
| 制度名 | 対象者 | 主な条件 | 支給内容 |
|---|---|---|---|
| 退職後の傷病手当金 | 健康保険加入者 |
| 給与の約2/3(標準報酬日額の2/3相当)を最長1年6ヶ月間支給 |
| 失業保険 | 雇用保険加入者 |
| 条件により数ヶ月間の給付(基本手当日額×所定日数) ※2025年4月以降は早期支給や教育訓練による制限解除あり |
| 自立支援医療制度 | 精神科通院者 | 医師の診断書で申請 | 医療費自己負担1割 |
- 傷病手当金は、退職後も「退職日に出勤していない」「1年以上健康保険に加入している」「退職日と同じ傷病で働けない状態が続いている」などの条件を満たせば、最長1年6ヶ月まで受給できます。
退職日に出勤してしまうと受給資格を失うため、最終出勤日には特に注意が必要です。 - 失業保険は、病気やケガで退職後すぐに働けない場合「受給期間延長」の申請ができ、最長4年まで受給開始を遅らせることが可能です。
また、精神疾患などで退職した場合は「就職困難者」と認定されることで、給付日数が延長されたり、給付制限が免除されたりする特例が適用されます(医師の診断書が必要)。 - 自立支援医療制度は、精神科通院が必要な場合に医療費自己負担が1割に軽減される制度です。
傷病手当金と失業保険の違い
| 給付名 | 受給できる人 | 主な受給条件 | 支給内容・期間 | 申請先 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 健康保険加入者 |
| 標準報酬日額の2/3相当額を最長1年6ヶ月間支給 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) または健康保険組合 | 「働けない」場合の生活保障 失業保険との同時受給は不可。 傷病手当金の受給中は、 失業保険の受給期間延長手続きを ハローワークで必ず申請。 |
| 失業保険 (雇用保険の基本手当) | 雇用保険加入者 |
| 退職前の賃金をもとに算出された 基本手当日額を所定日数(90日~330日など)支給 | ハローワーク | 「働ける」状態で求職活動が必要 病気療養中は原則受給不可。 治療後は速やかに切り替え申請を。 |
- 傷病手当金は、病気やケガで「働けない」場合の生活保障で、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に申請します。
失業保険よりも支給額が高いことが多く、退職後はまず傷病手当金を受給し、働ける状態になったら失業保険に切り替えるケースが一般的です。 - この場合、失業保険の受給期間(原則退職後1年以内)は、傷病手当金の受給中に経過してしまうため、必ずハローワークで「失業保険の受給期間延長手続き」を行っておく必要があります。
延長申請をしておけば、最大3年間(合計で4年以内)まで受給開始を先送りでき、治療後に失業保険を受給できます。 - 失業保険(雇用保険の基本手当)は、「働ける」状態で求職活動を行う人が対象で、申請先はハローワークです。
病気やケガの療養中は原則として受給できませんが、治療が終わり、就労可能となった場合は、以下の流れで申請を進めます。
- まず、ハローワークで「就労可能証明書」や「主治医意見書」などの専用書類を受け取ります。
- その書類を主治医に持参し、現在の健康状態や就労可能かどうかについて記入してもらいます。
医師は「症状が安定し、就職活動が可能」と判断した場合に証明書を発行します。
医師の証明書には、就労の可否、就労上の配慮事項、病状や障害の状態などが記載されます。 - 記入済みの証明書をハローワークに提出し、失業保険の受給手続きを行います。
この証明書により、ハローワークは「就職の意思と能力がある」と判断し、失業保険の受給が開始されます。
※この療養期間中に受給期間延長の手続きをしておくことで、治療後にスムーズに失業保険受給へ移行できます。
※主治医の証明書が発行できるのは、定期的な通院治療の実績がある場合に限られるため治療中から通院記録を残しておくことも重要です。
退職が言い出せないときの“心強い味方”

退職代行サービスの活用
どうしても自分で伝えられない場合は、退職代行サービスや弁護士による退職代行も利用できます。
| サービス名 | 特徴 | サポート内容 | おすすめポイント |
|---|---|---|---|
| セルフ退職ムリサポ! | 退職交渉支援ノウハウ提供 | 自分で交渉したい人向けにノウハウ・アドバイスを提供 | 自分のペースで進めたい方に最適 |
| 弁護士法人ガイア法律事務所 | 弁護士による退職代行 | 法律の専門家が会社と直接交渉・退職手続きも安心 | トラブルが不安な方や法的サポートが欲しい方に |
| 労働組合運営の退職代行ネルサポ | 労働組合が運営 | 団体交渉権を活かした会社対応・有給消化や未払い賃金請求もサポート | 会社との交渉力重視・費用も抑えたい方におすすめ |
| 退職代行モームリ | 即日対応可能な退職代行 | 会社とのやり取りを全て代行・スピーディーな手続き | すぐに辞めたい方や直接話したくない方に |
退職後の「心の回復」と「新しい人生」へのヒント
退職後は「回復」と「リセット」の時間
退職後は、心身をしっかり休めることが最優先です。
「何もできない自分」に焦りや罪悪感を感じるかもしれませんが、 回復には時間が必要です。
今は「休むこと」が“仕事”だと考えてください。
焦らず、少しずつ「自分らしさ」を取り戻す
再就職や新しい挑戦は「心が回復してから」
無理に「すぐに働かなきゃ」と思わなくて大丈夫です。
まずは自分の心と体をしっかり整えてから、 「どんな人生を送りたいか」「どんな働き方が合っているか」を見つめ直しましょう。
| やるべきこと | ポイント |
|---|---|
| 十分な休息をとる | 心身のリセットが最優先。無理に動かなくてよい |
| 規則正しい生活を送る | 生活リズムが安定することで回復が早まる |
| 適度な運動や趣味を取り入れる | ストレス発散・気分転換に効果的 |
| カウンセリングや就労移行支援を活用 | 専門家のサポートで自己理解や社会復帰の準備ができる |
| 公的制度の申請 | 傷病手当金・失業保険・自立支援医療などを活用 |
失業保険を受給しながら職業訓練を受けるという選択肢
退職後、「すぐに再就職は不安…」と感じる方も少なくありません。
そんな時、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給しながら職業訓練(ハロートレーニングなど)を受けることは、とても有効な選択肢です。
実際、これまで多くの方が職業訓練の受講を経て再就職に成功した事例が報告されています。
職業訓練の主なメリット
失業保険と職業訓練で再出発
私が再就職支援に携わるなかで出会った、20代女性クライアントの実例をご紹介します。
彼女は大学を卒業後、新卒で正社員として工場に入社し、2年間勤務していました。
几帳面で真面目な性格が印象的な方です。
退職のきっかけと不安
大学卒業後、念願の正社員として工場勤務をスタート。しかし現場では先輩からの強い圧力や暴言、過酷な作業環境、体力的な負担が重なり、心身ともに限界を感じて退職を決意しました。
真面目で責任感が強い彼女は、「このまま続けるべきか」「自分は社会でやっていけるのか」と深く悩み、退職後は将来への不安でいっぱいだったそうです。
職業訓練との出会い
再就職支援の相談の中で、彼女の丁寧な仕事ぶりや几帳面さを活かせる職種として、パソコン事務の職業訓練コースを提案しました。
事務職は未経験でしたが、「新しいことに挑戦したい」という前向きな気持ちで受講を決意。
失業保険を受給しながら安心して学べる環境も、彼女の背中を押しました。
訓練期間で得たもの
訓練期間中は、持ち前の几帳面さを活かし、Word・Excelなどのパソコンスキルを一つ一つ丁寧に習得。
簿記やFP(ファイナンシャルプランナー)資格にも挑戦し、見事合格しました。
真面目な性格が学びの成果に直結し、クラスメイトからも信頼され、時にはサポート役を任されることもありました。
また、同じ目標を持つ仲間と励まし合うことで、少しずつ自信を回復。
訓練が進むにつれて、「自分にもできることがある」と前向きな気持ちになっていきました。
就職活動の苦労と成功
訓練修了後、未経験からの事務職への応募で何社も落ちるという苦しい時期もありました。
新卒入社から2年の経験がありながらも、異業種・未経験分野への転職は決して簡単ではありませんでした。
さらに、彼女には「運転が苦手」という弱点がありました。
自宅近郊の職場は車通勤が一般的な地域でしたが、運転に自信がなく、都市圏での電車通勤を希望。
事務職未経験に加え、都市圏の長時間電車通勤という条件は、採用においてもハードルとなり、応募先の選択肢が限られ、より厳しい戦いとなりました。
それでも諦めずに応募を続け、訓練で学んだ応募書類の書き方や面接対策を活かして挑戦し続けました。
新たなスタート
退職からちょうど1年後、ついに希望していた都市圏の正社員事務職に採用されました。
新しい職場では、几帳面で真面目な性格が評価され、仕事も順調にスタート。
訓練で得た資格やスキルが即戦力となり、上司や同僚からも信頼を得ています。

失業期間は本当に不安でしたが、職業訓練に通いながら失業保険をもらえたことで、生活の心配をせずに勉強に集中できました。
新しい友達もでき、学生時代のような充実感を味わえたのも大きな財産です。思い切って一歩踏み出して本当に良かったです。
几帳面で真面目な方ほど、職業訓練での学びや仲間との出会いが大きな力になります。
新卒入社後の早期離職やキャリアチェンジに悩む方も、失業保険と職業訓練を活用した再出発は、不安な気持ちを安心に変え、新しい自分に出会うきっかけとなるはずです。
職業訓練と失業保険を活用することで、安心して新たなスタートを切ることができます。
再就職への不安がある方は、ハローワークで相談し、自分に合った職業訓練を検討してみてください。
未来をひらく!職業訓練で詳しく説明しています。
あなたの未来へ。心からのエール
うつ病や適応障害で退職を考えるのは、あなたの人生を守るための“強さ”です。
「会社に迷惑をかけてしまう」「自分のせいで…」と自責の念にとらわれる必要はありません。
あなたの健康と人生は、何よりも大切です。 退職を決断したら、「会社への伝え方」「診断書の活用」「傷病手当金や失業保険」など、 制度をフル活用して、安心できる生活を整えましょう。
どうしても自分で進めるのが難しいときは、「退職代行」や「専門家」の力を借りてください。 あなたの未来は、今よりもっと明るくなります。
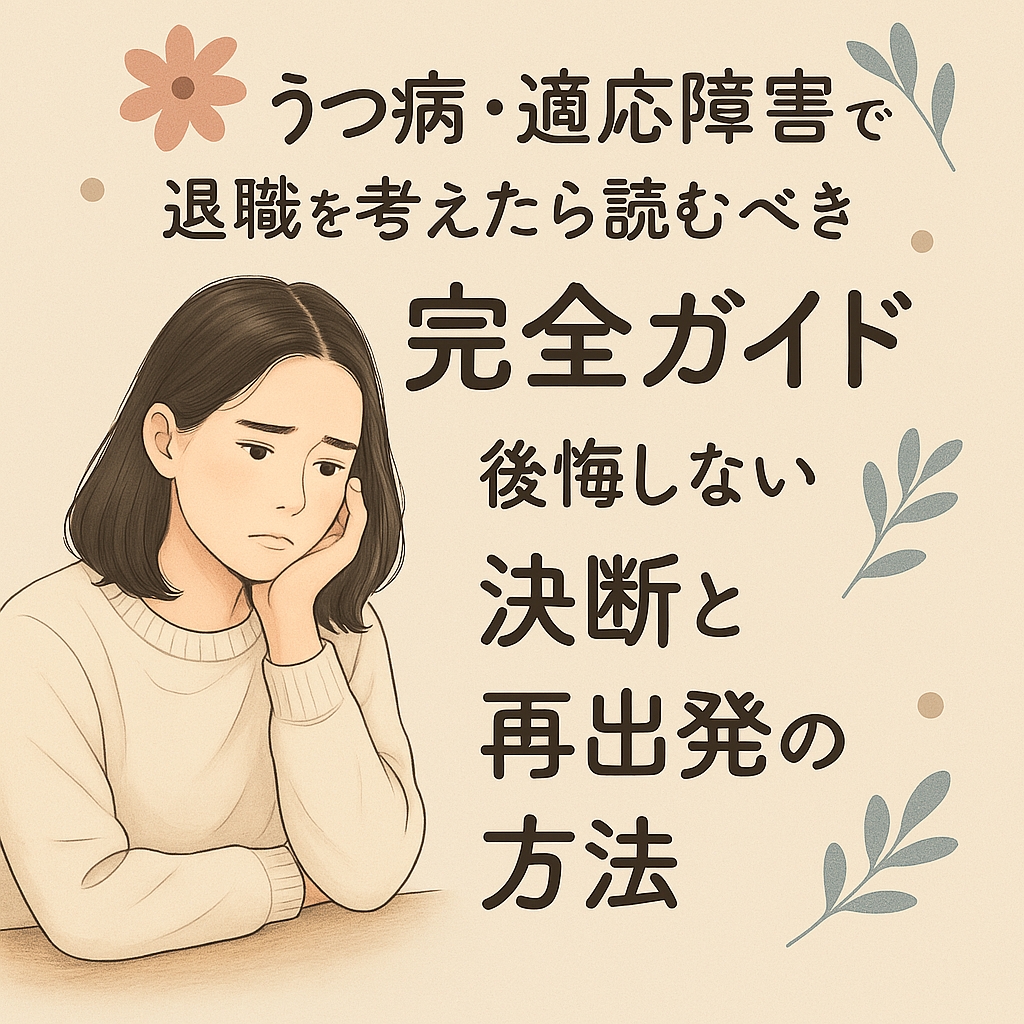
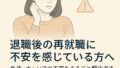
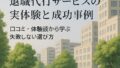
コメント