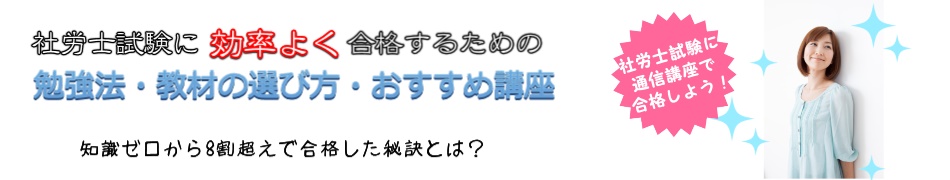社労士試験に効率的に合格する勉強法
あなたは社労士試験に効率よく合格したいですか?
私は2回目の受験でやっと合格できたのですが、1回目のこの社労士試験の不合格がわかったときから、
「どうやったら確実に社労士試験に合格できるのか」、これを真剣に考えました。
すぐに答えが出るものでもなかったですが、受験期間中は常にそのことを意識して勉強していました。
その過程の中で、資格試験特有の傾向を肌で感じることができたんだと思います。
また、合格した後の今までに、数え切れないほどの社労士合格体験記や合格マニュアル(メルマガなど)を読んできて受験時代よりもより一層資格試験の攻略法を確信することができました。
そして、私は、社労士試験に限らず難関の資格試験に合格するために必要な重要なポイントが大きく3つあると思うようになりました。
この3つのポイントはとても重要で、試験合格を左右するものであるにもかかわらず、残念ながら多くの受験生ははっきりと意識することなく本試験を迎えていると思います。
それは、
- テキスト中心学習なのか、問題演習中心学習なのか
- いかに勉強を継続するか
- 解答の確率論を理解しているか
この3つです。
多くの受験生が合格したいと思って一生懸命頑張ってもなかなか結果が出ない(合格できない)のは、多くの先入観や誤った情報、イメージを持っているのかなと思います。
なぜ、そのようなことが言えるかというと、自分も勉強方法に悩んでうまくいかなかった経験があるからです。
多くの受験生は、まずテキストをじっくり読んだり講義を聴いたりして科目の理解を深め、それから、あるいは同時に問題演習を行なうという流れになると思います。
でも、テキストを読んで内容を理解できたと思っても、問題が解けるレベルとは大きな隔たりがあって、全く問題が解けないという事実に驚くでしょう。
そうはいっても、社会保険労務士の試験勉強を始めるにあたり、テキストを学習のメインにする受験生はやはり多いでしょう。
独学の受験生は市販のテキスト学習になるでしょうし、通学や通信を利用する受験生は、その講座のテキストを学習の中心で利用される場合が多いでしょう。
しかし、実際にテキストを手に取った方はお分かりだと思いますが、
あまりに分厚いボリュームに圧倒されるのではないでしょうか?
そんな分厚いテキストを何度も繰り返し読むことはとても大変な作業です。
しかも、その内容を理解し暗記しようと思ったら、その学習だけで本番を迎えてしまいかねません。
私も、社労士試験受験1年目はテキスト中心の勉強でしたが、テキスト読みだけでかなりの時間を取られ、しかも、何度も繰り返し読んだとしても、問題を解けるようにはなりませんでした。
この年は、合格は難しいなと感じながら勉強していた記憶があります。
合格できないだろうと思いながら勉強するのはつらいものです。
振り返ってみると、社会保険労務士試験には、受験生に大きく立ちはだかるいくつかのハードルがあると感じました。
それは、以下の様なことです。
- 膨大な出題範囲である
- 重箱のスミを突くような超難問が出題される
- テキストを読んでも問題が解けない!
特に3番目に挙げた、テキストを読んでも問題が解けないという事実は1年目の私を苦しめました。
しかし、
2年目の挑戦では、
学習方法を変えることで合格を手にすることができました。
択一式で8割を超える結果を出せたのは、勉強法を変えたからだと断言できます。
では、どういった勉強法なのか?
それは、テキストの取り組みを大きく変えた勉強法です。
問題演習を学習の中心に置く勉強法なんですが、学習の初期から問題演習中心の勉強法です。
このように書くと、「そんなことは知っている!」
と言われてしまいそうですが、私はおススメするのは少しやり方が違うかもしれませんので参考にしていただければと思います。
まず、問題集は最初から解く必要はないのです。
最初は問題集を読んでいくのです。
問題集は「問題と解説のついた」テキストだと思って読めばいいのです。そして繰り返しでその問題(5択式なら各肢全部)が完璧に解けるように仕上げます。
これで、択一式の得点は確実に上がります!!
社労士受験生の受験期間が長期化しているそうです。
確かに、合格率からすればそれも納得できますね。
そして、受験生の中には、何年も勉強は一生懸命やっているけど、なかなか択一式で合格ラインに達しない。
そんな受験生も多いはずです。
すると、自分の能力では社労士試験は届かないのか?
そっちに意識がいってしまう受験生が多いです。能力の問題に捉えてしまう・・・。
確かに、連続して何年も不合格が続くと、そのように思ってしまいがちです。
でも、少し厳しい言い方をすれば、それはあなたの能力の問題ではなくて、勉強の仕方の問題だと思うのです。
別の言い方をすれば、効率の悪い勉強法でも、ひたすら勉強するモチベーションが継続できて地道にハードな勉強を続けられるのであれば、難関試験といえども、いずれはなんとか合格してしまうものだとも思います。
でも、効率的に最短で社労士試験に合格したいなら、
勉強量で満足せず、無駄な時間であるノート纏めとかも止めて、繰り返しテキストを読むこともせず、疑問点に捉われて深入りして時間を費やすことなく、
とにかくひたすら問題をたくさん解いてみてください。
そして、すべて大量の問題を本試験まで完璧に仕上げること。これで択一式で合格点をとれるレベルに達することができると信じています。
色々な事情の受験生がいると思います。
今年必ず社労士試験に合格しなければいけない、合格・不合格でも、今年の受験最後という方から、できれば受かりたいけど今年は無理かな、という気持ちで勉強している人、少しテキストを読んでみたけどあまりの範囲の広さに圧倒されている人、全く本試験レベルの問題が解けなくて途方にくれている人・・・。
いろんな形があると思います。
でも、せっかく、社労士試験合格を志したのなら、効率よく合格してほしいと思います。
このサイトでは、上記の3つの合格ポイントと共に、本試験で失敗しないための回答テクニックも掲載しています。悩める社労士受験生に少しでも参考になれば幸いです。
さらに、他にも社労士試験に合格するために必要な勉強法について書いていきます。